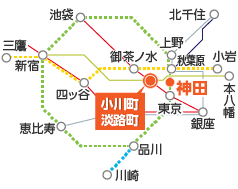新民法について(1)【消滅時効】
2020年4月1日から新民法が施行されました。今回の改正は多岐にわたりますが、主なところをご紹介します。今回は消滅時効です。
1.主観的起算点の導入
改正前の消滅時効期間は、権利を行使できる時から原則10年でした(改正前民法第167条)。改正後は、①権利を行使できる時から10年という時効期間に加えて、②「権利を行使できることを知った時」から5年という主観的起算点からの時効期間が追加されました。原則として、①または②のいずれかを満たした場合に、債権が時効により消滅します(改正後民法第166条1号、2号)。
2.職業別の短期消滅時効の特例及び商事消滅時効の特例の廃止
改正前は、一定の債権については、例外的に消滅時効期間1~3年とする職業別の短期消滅時効の特例を設けていました(改正前民法第170条から同法174条)。また、商行為によって生じた債権については消滅時効期間を5年とする特例も設けていました(旧商法第522条)。
今回の改正により、上記特例はいずれも廃止され、全て上記1と同様になりました。
3.生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての特例
改正前の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は、不法行為に基づく場合は損害及び加害を知った時から3年、債務不履行に基づく場合は権利を行使することができる時から10年でした。今回の改正で、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、その原因が債務不履行であるか不法行為であるかを問わず、主観的起算点から5年、客観的起算点から20年に統一されました(改正後民法第167条、第724条の2)。
4.不法行為の消滅時効
不法行為の時から20年という期間は、権利の消滅を阻止することができない除斥期間ではなく、消滅時効期間であることが明記されました(改正後民法724条第2号)。そのため、後述する時効の完成猶予や更新を行うことによって、時効消滅を阻止し得ることが明らかとなりました。
5.完成猶予と更新
改正前民法の時効の完成の障害事由には、時効の「停止」と「中断」がありました。
今回の改正では、意味を分かりやすくするため、事由の発生により進行していた時効期間の経過が零となり、あらたに零からスタートするという「更新」と、猶予事由が発生しても、時効は進行し続けるが、本来の時効期間の満了時期を経過しても、所定の時期を経過するまでは時効が完成しない効果のある「完成猶予」の二つの概念に再構成されました。
6.適用関係(経過措置)
改正後の消滅時効期間が適用されるのは、施行日である2020年4月1日以降に発生した債権です。2020年4月1日より前に、発生した又は債権発生の原因となる法律行為(契約など)がなされた債権については、改正前の消滅時効期間が適用されます(民法附則10条1項、同条4項)。
(文責:横山愛聖)